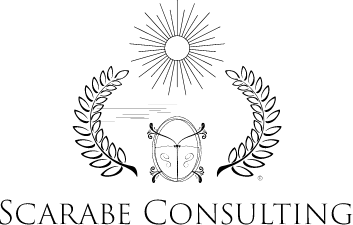TOPICSトピックス
その決算対策、損してませんか?全体設計なき節税の落とし穴
「法人の経費になるこんな商品はいかがですか?」─決算が近づくたび、様々な営業担当者からこのような提案を受け、「税金が安くなるのなら…」と必要性のはっきりしない商品をなんとなく購入された経験はありませんか。
確かに、目先の節税効果は得られるかもしれません。しかし、「節税」だけに注目した結果、数年後に思わぬ税負担や資金繰りの悪化に直面するケースもあるため、注意が必要です。
私がこれまでお会いした院長先生の中にも、「節税のつもりが、結果的に損をしてしまった」という苦い経験をお持ちの方が少なくありません。なぜこのようなことが起こるのでしょう。今回は、節税が自己目的化することの危険性と、出口まで見据えた全体設計の重要性について、実際の事例を交えながら解説したいと思います。
生命保険の「損金」にこだわりすぎた結果
Aクリニックの院長先生は、ある保険会社の営業担当者から「全額損金の保険があります」という提案を受けました。年間保険料600万円で、しかも全額が損金算入できるため、法人税負担の軽減効果を考えると実質的な負担は200万円程度。「これは魅力的だ」と感じ、すぐに加入を決断されました。
確かに加入当初は、毎年300万円の経費計上により節税効果を実感できました。しかし、後に資金が必要になり保険を解約した際、予想外の事態に直面したのです。解約返戻金1,500万円が雑収入として計上されることで法人の利益が大幅に増加。結果として想定以上の税負担が発生することになったのです。
さらに問題だったのは、キャッシュベースで考えた場合の収支です。支払った保険料総額3,000万円に対し、手元に戻ってきたのは1,500万円。つまり、実質的に1,500万円ものキャッシュが目減りしてしまったのです。保険料支払時には節税効果を得られましたが、解約時には逆に税負担が発生し、さらにキャッシュも大幅に減少するという二重の打撃を受けることになりました。A院長は「節税効果ばかりに目を向けて、解約時の税務処理を軽視していた」と振り返られています。
なぜこのような失敗が起こるのか
開業医特有の「重税感」から、「とにかく税金を減らしたい」という感情が先行し、単年度の節税効果ばかりに注目してしまうことが主な原因です。また、商品の仕組みを十分に理解していない営業担当者から、目先のメリットだけを強調した提案を受けることも一因です。
真の節税とは「全体最適」を目指すこと
では、どのような考え方で節税に取り組めばよいのでしょうか。重要なのは、節税を単独で考えるのではなく、経営全体の中で「全体最適」を目指すことです。
重要なポイントは3つあります。第一に、キャッシュフローの最大化。節税のための支出で必要な手元資金まで減少するようでは本末転倒です。第二に、課税の繰り延べと回避の区別。生命保険などは「繰り延べ」であり、将来の課税を前提とした戦略が必要です。第三に、出口戦略の明確化。解約時や売却時の税務処理を事前に把握しておくことが不可欠です。
正しいアプローチとは
先ほどの生命保険の事例では、どのようなアプローチが正しかったのでしょうか。
入口の損金算入効果だけでなく、出口となる将来の事業計画との整合性も考慮すべきでした。例えば、将来的に役員退職金の支給を予定しているのであれば、その時期に合わせて解約のタイミングを設計し、退職金原資として経費化する、といったことです。
このように、単年度の節税効果だけでなく、法人の中長期的な資金計画と連動させることで、より効果的な税務戦略を構築することができます。
「目先の節税」から「全体設計に基づく節税」へ
節税は手段であって目的ではありません。真の目的は、「手取り収入の最大化」と「将来に向けた資産形成」です。目先の節税効果に惑わされず、キャッシュフローへの影響、中長期的な税負担の見通し、出口戦略の明確化という視点で全体最適を目指すことが重要です。
「目先の節税」から「全体設計に基づく節税」へ。この転換こそが、医業経営者にとって大切ではないでしょうか。