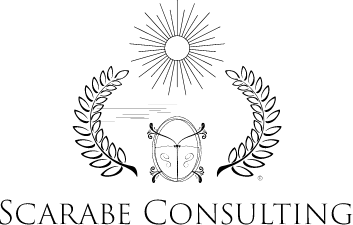TOPICSトピックス
毎月分配型ファンドの魅力と誤解 本当に得してる?
毎月分配型ファンドの魅力と誤解
「毎月分配型ファンド」が、ここ数年で再び注目を集めています。毎月一定額の分配金が得られる仕組みが、安定した収入を求める人々にとって非常に魅力的に映るのでしょう。しかし、その仕組みやリスクを十分に理解しないまま投資を行うと、期待した成果が得られない可能性もあります。今回は、毎月分配型ファンドの仕組みとリスクについて掘り下げ、投資目的に適した商品を見直すためのヒントをお伝えします。
分配金=運用益ではない
「分配金が多いほど、このファンドは儲かっている」と感じるのは自然な感覚かもしれません。しかし、分配金は必ずしも運用益を反映したものではありません。
分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。普通分配金は運用益から支払われますが、特別分配金は元本の一部が払い戻される形で支払われるため、元本が減少するリスクを伴います。分配金が定期的に支払われることは魅力的ですが、特別分配金が多いファンドでは、資産が減少している可能性に注意が必要です。
再投資型ファンドとの比較
分配型ファンドでは、分配金を払い出すため、複利効果を十分に活用できず、再投資型ファンドに比べて資産成長が抑えられます。以下の図は、運用利回り10%のもと、分配型ファンドと再投資型ファンドの資産推移を比較したものです。分配型ファンドでは、毎年5%の分配金を払い出すことで資産の増加が鈍化していることがわかります。このように、分配型ファンドは長期的な資産形成には不利であるといえます。

特別分配金が元本に及ぼす影響
特別分配金は、元本を払い戻す形で支払われるため、資産の減少を招くリスクがあります。例えば、運用利回り5%のファンドで毎年元本の10%を分配金として払い続けた場合、分配金が運用益を上回るため、元本は年々減少します。この影響により、10年後には元本の約半分以下にまで減少する可能性があります。高い分配金は一見魅力的に映りますが、運用益を超える分配金が続く場合、元本が減少し、資産運用全体に深刻な影響を与えるリスクがある点に注意が必要です。
短期的な高利回りに惑わされない
コロナショック以降の経済回復により、多くのファンドが一時的に高い利回りを示しています。しかし、この「高利回り」は市場環境による一時的なもので、必ずしもファンドの健全性を示しているわけではありません。
高い分配金を維持するために無理な運用が行われ、元本が減少するリスクもあります。分配型ファンドを選ぶ際は、分配金の背景やファンドの健全性を慎重に確認することが重要です。
投資目的を再確認しよう
毎月分配型ファンドは、退職後の生活費補填やキャッシュフロー確保を目的とする場合に注目されることがあります。ただし、特別分配金の割合が高いファンドでは、元本が早期に減少し、短期的にも長期的にも運用効率を損なうリスクがあります。
キャッシュフローを確保する手段としては、自動売却機能を活用したファンドやETF、配当重視型の商品も選択肢となります。これらは柔軟に資金を管理しつつ、効率的な運用を可能にします。
資産を増やすことが目的であれば、再投資型ファンドや積立型投資信託など、複利の力を活用できる商品が王道です。いずれにしても、ライフプランに合った投資目的を明確にし、必要に応じて専門家の助言を得ることをおすすめします。